
- 2025.05.20
- プレスリリース
(一社)九州MaaS協議会 2025年度定時総会の開催について


「九経連 第65回定時総会」招集のご通知 ※議案書等掲載

【6月15日開催】「地域脱炭素フォーラム2025 ~地域脱炭素2.0に向けた官民連携の更なる強化~」のご案内
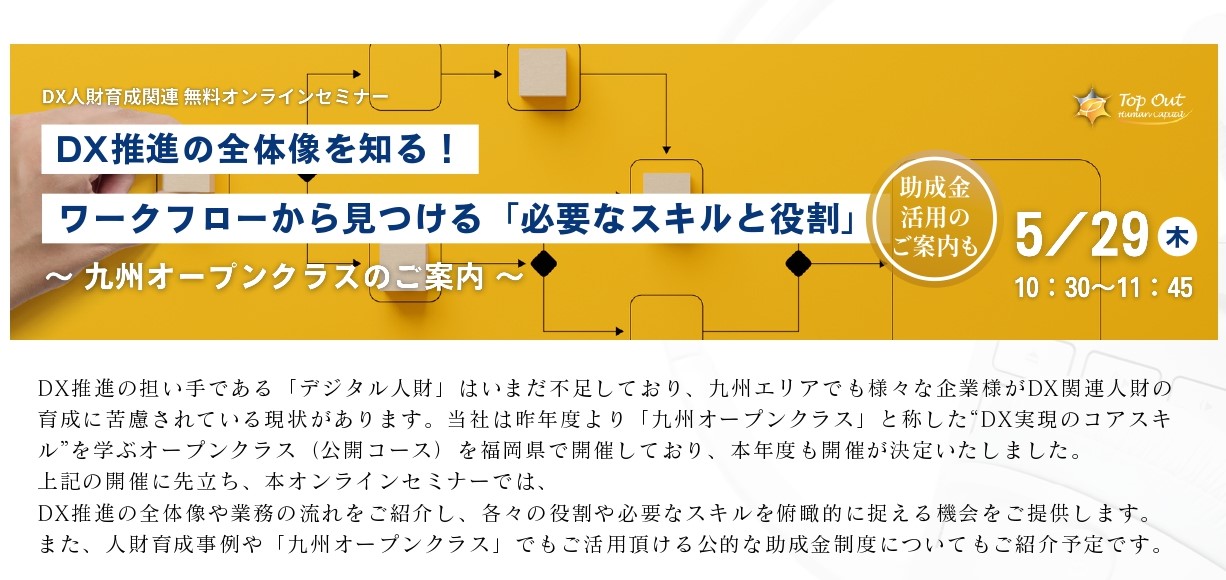
【5月29日開催】「DX人材育成関連セミナー(九州オープンクラスご紹介)」のご案内

弊会会長人事に関する新聞各紙の記事について

九経連事務局休業のお知らせ(4月28日)

非住宅木造建築「モクビル」ご検討のお願い ~あなたの会社も木造へ!事務所・店舗・倉庫など非住宅も~

第181回理事会(5月12日 福岡市・グランド ハイアット福岡)

【5月15日開催】第5回CN推進研究会

【4月23日開催 】2025年度 第15回産学連携懇談会

【3月14日開催】第5回 九州・沖縄・山口ESG投融資推進会議

【2025年3月4日~9日】「九州・ベトナム経済交流ミッション2025」実施報告

第180回理事会(3月26日 福岡市・ソラリア西鉄ホテル福岡)

九経連は1961(昭和36)年4月、経団連、関西、中部に次いで全国で4番目の総合経済団体として設立され、2021(令和3)年には創立60周年を迎えました。
内外の社会・経済などに関する諸問題について調査研究を行い、九州・沖縄経済界としての意見を取りまとめ、実現に向けて、政府・関係機関等に対する積極的な提言・要望や様々な活動に取り組んでいます。
共生や共感によって、成長と心の豊かさが好影響を与え合い、
新たな価値を共創する持続可能な地域を目指します。
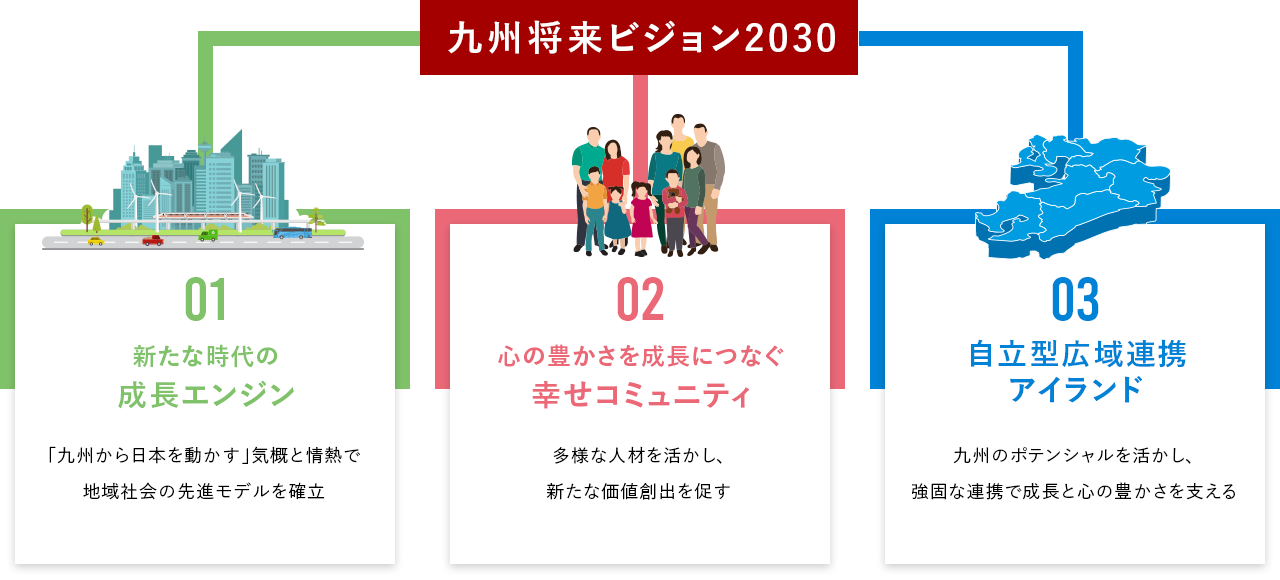
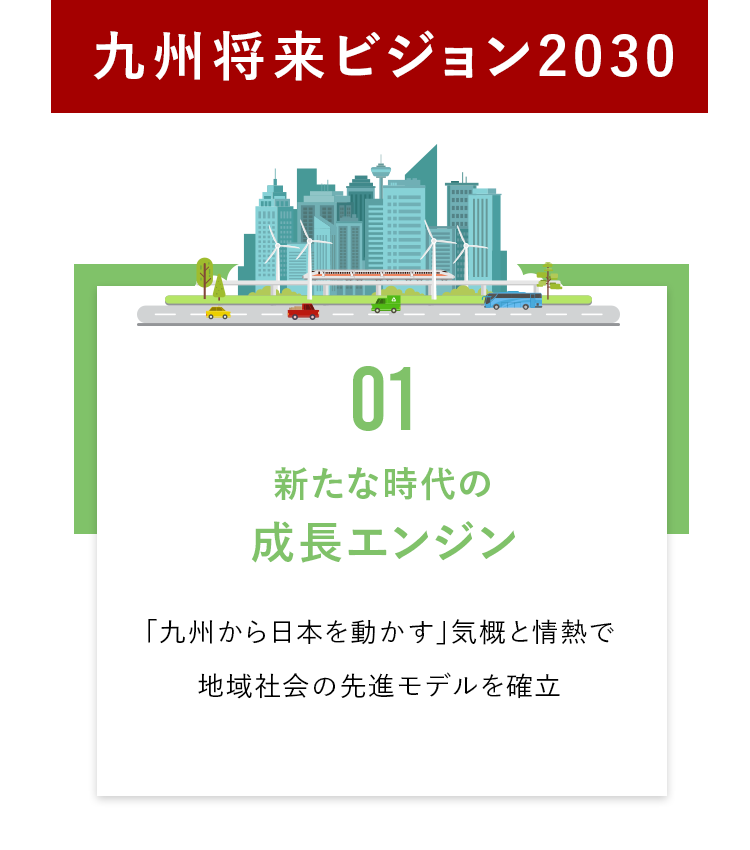
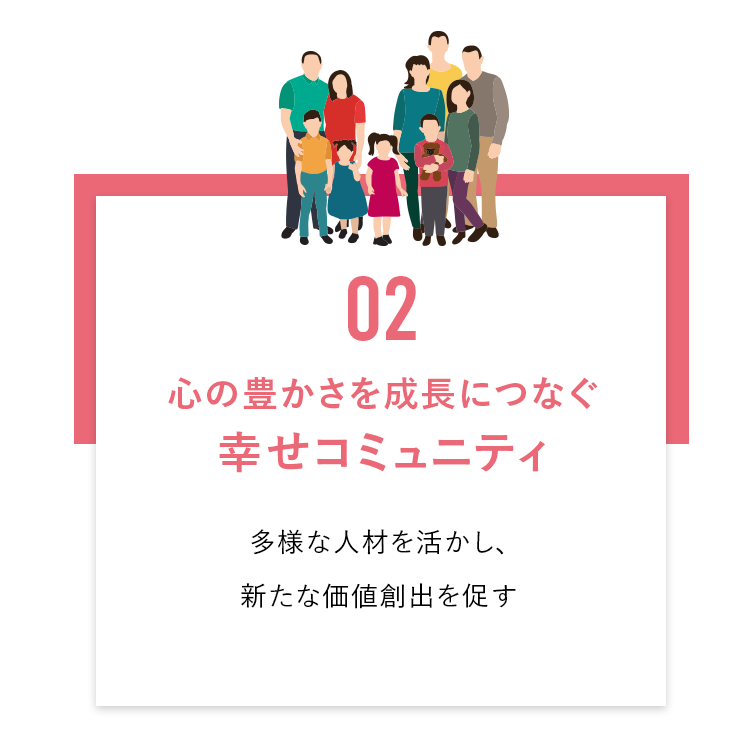
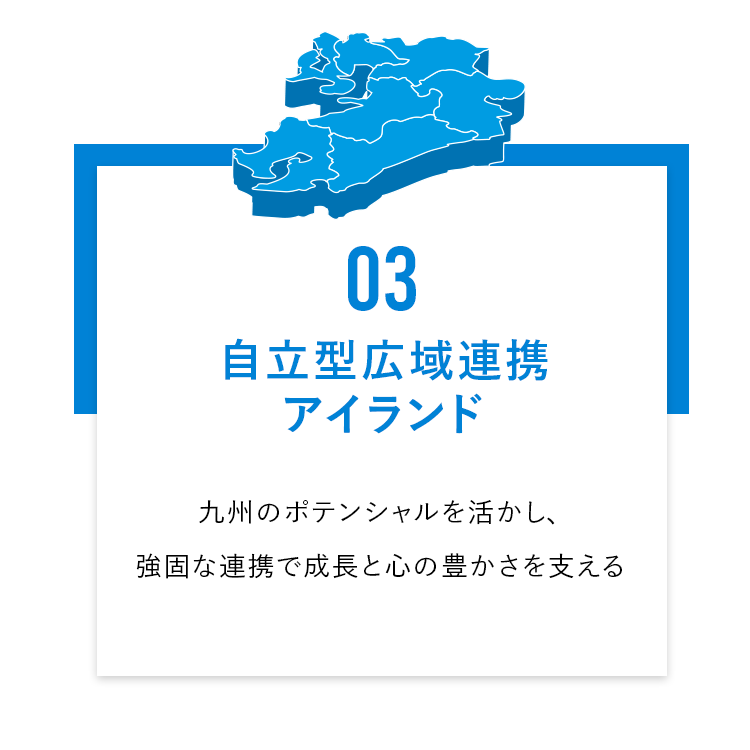
2021年以降、九経連は2030年のありたい姿およびその実現に向けた課題を踏まえ、
取り組むべき重要施策をアクションプランに落とし込み、産学官民の連携を促進しながら、
私たちのミッション 九州から日本を動かす 気概のもと活動を展開していきます。